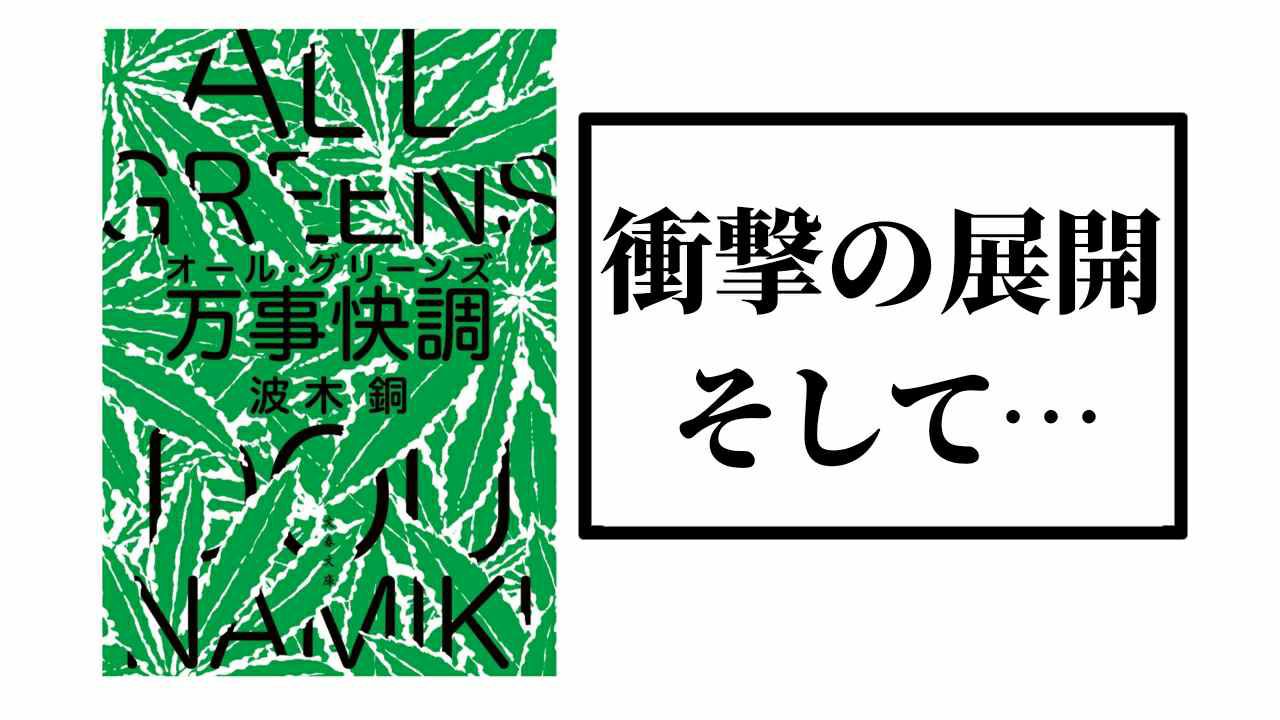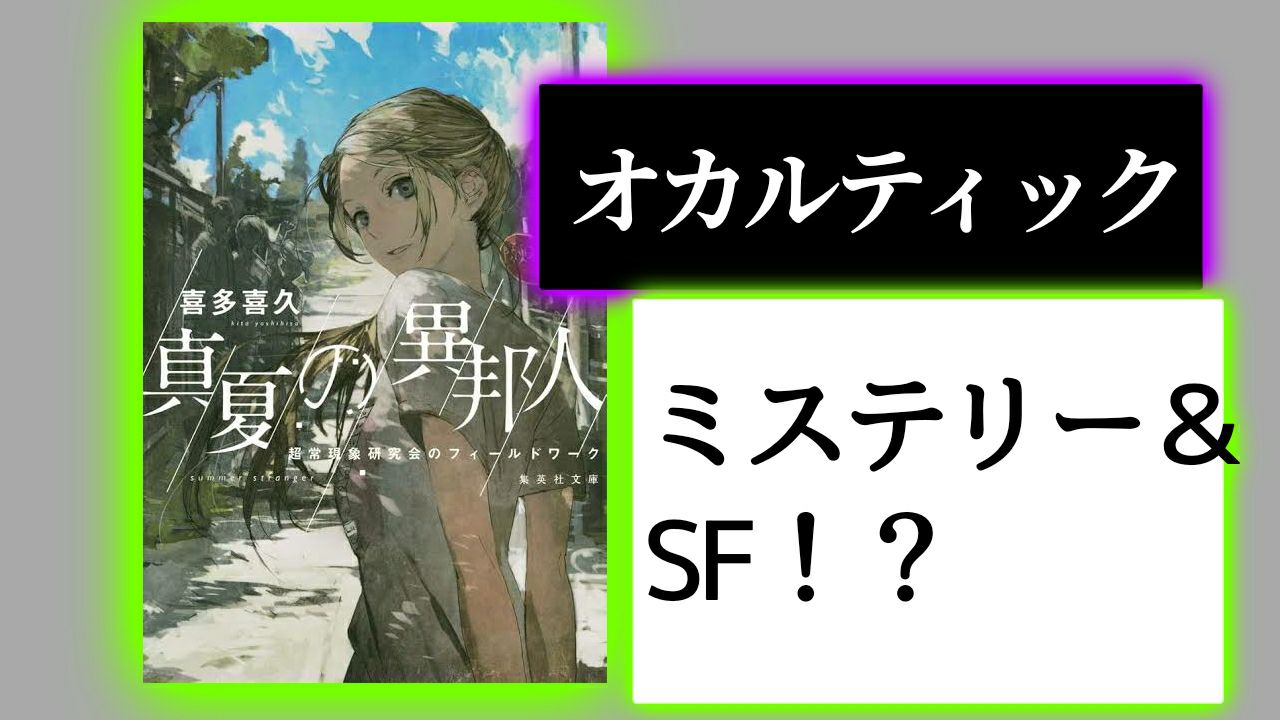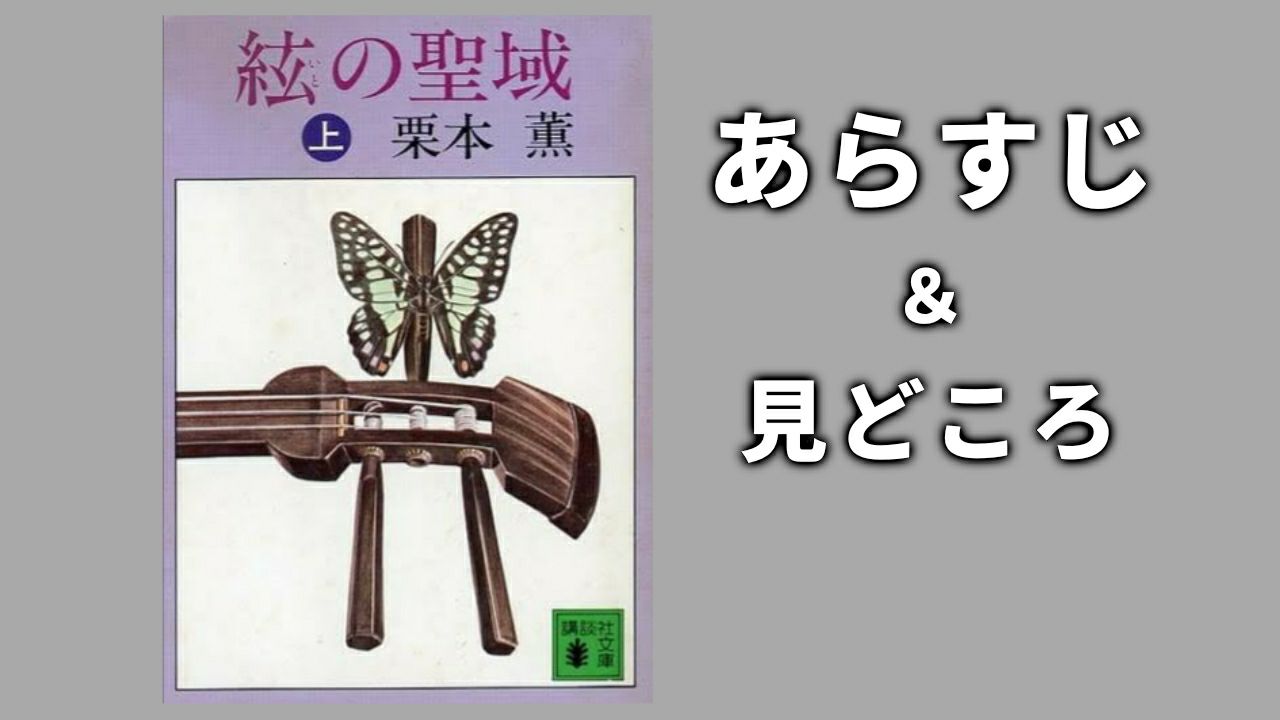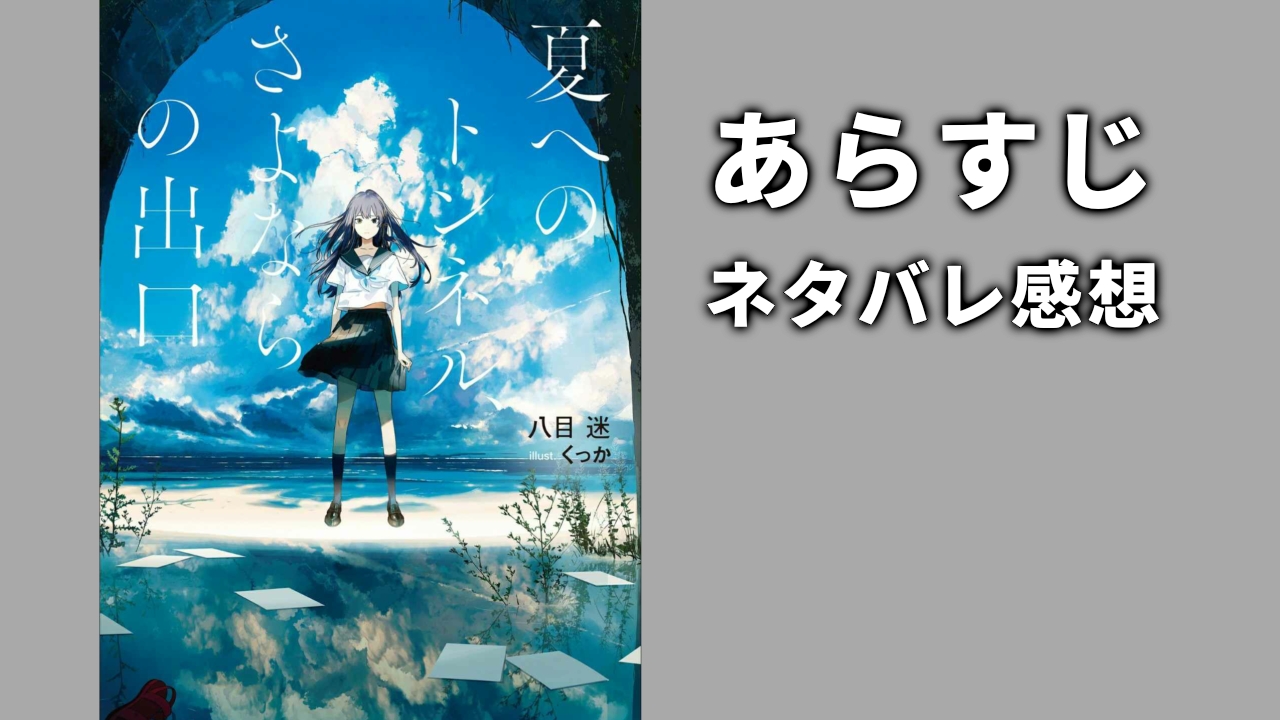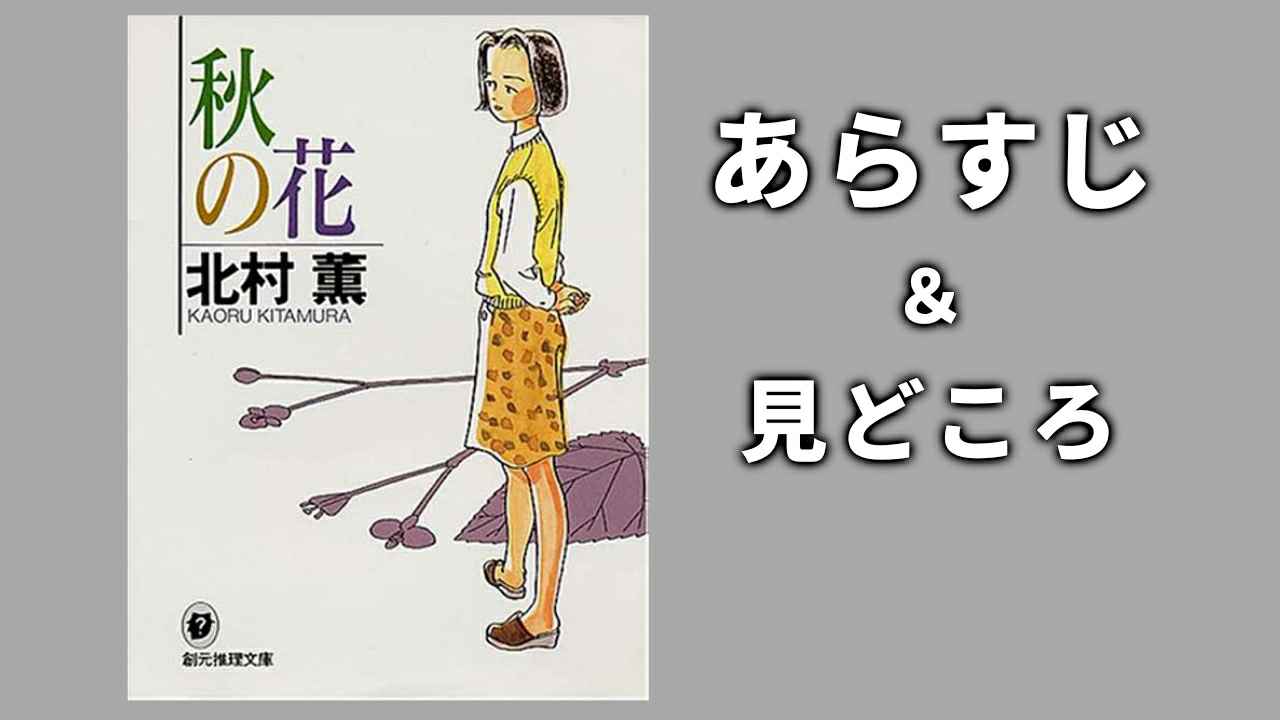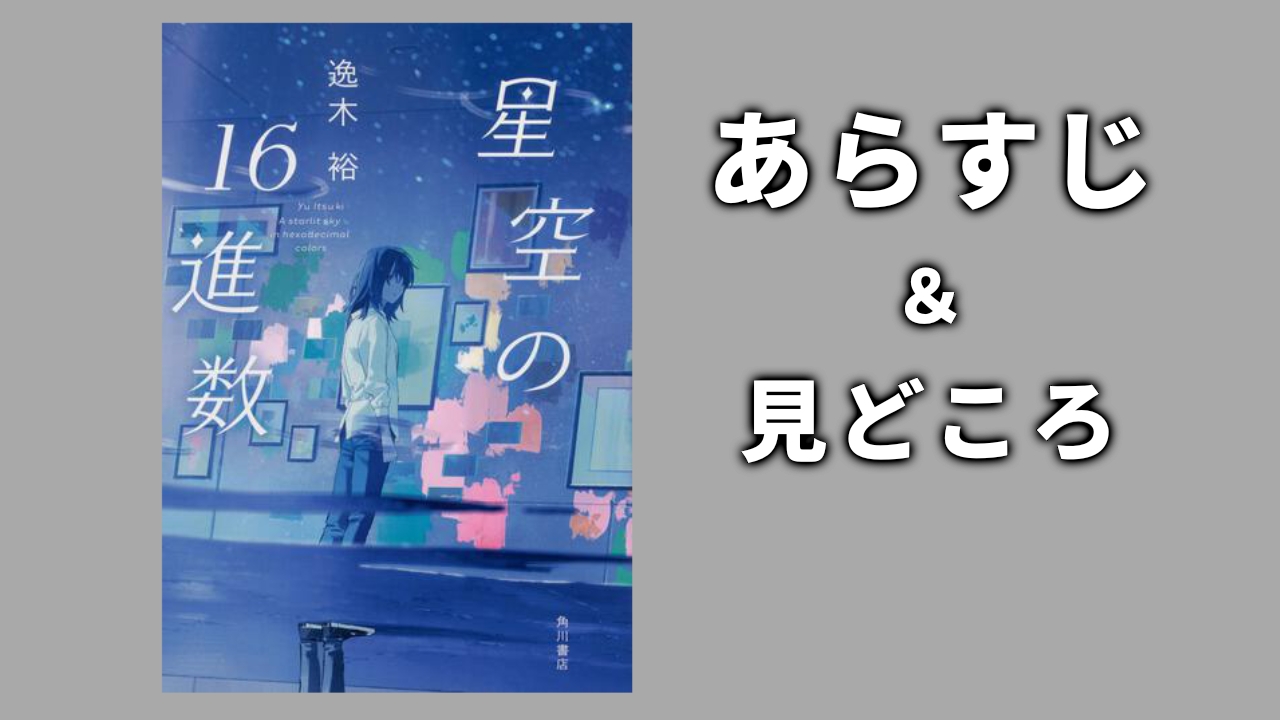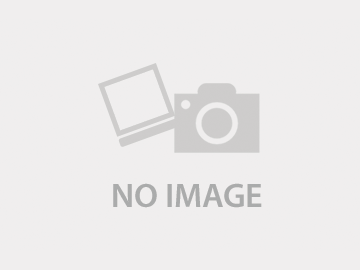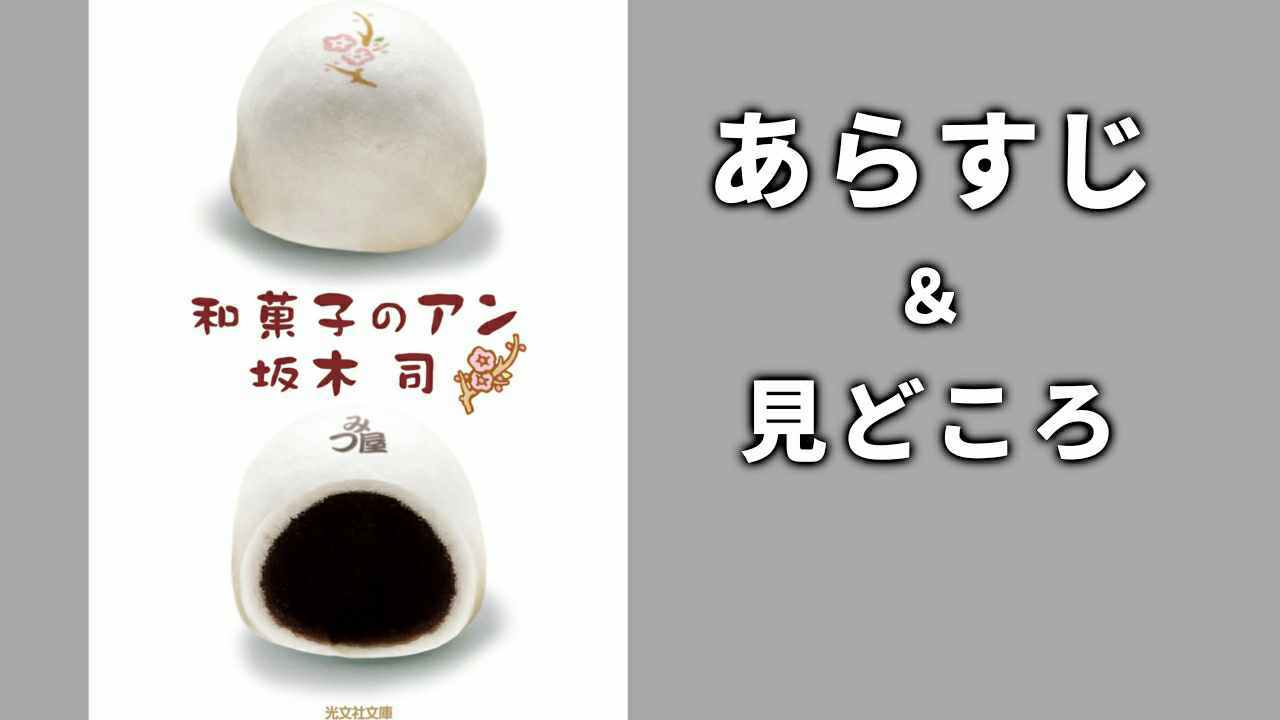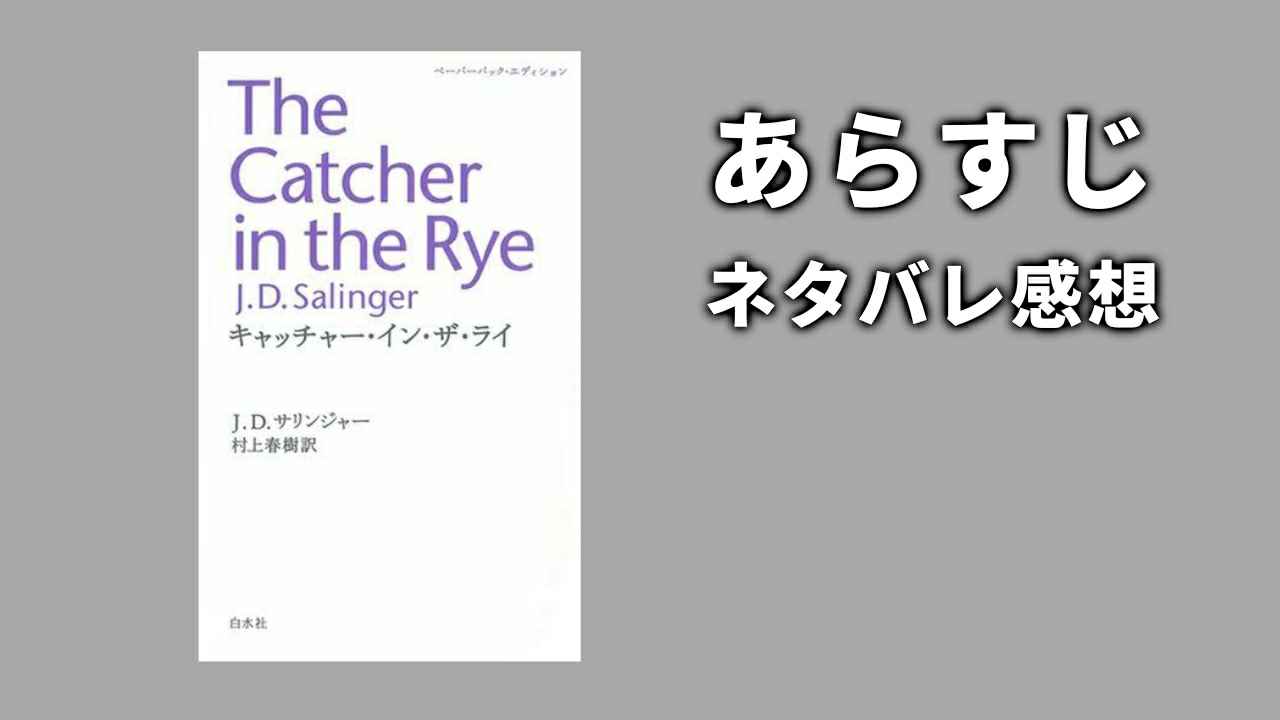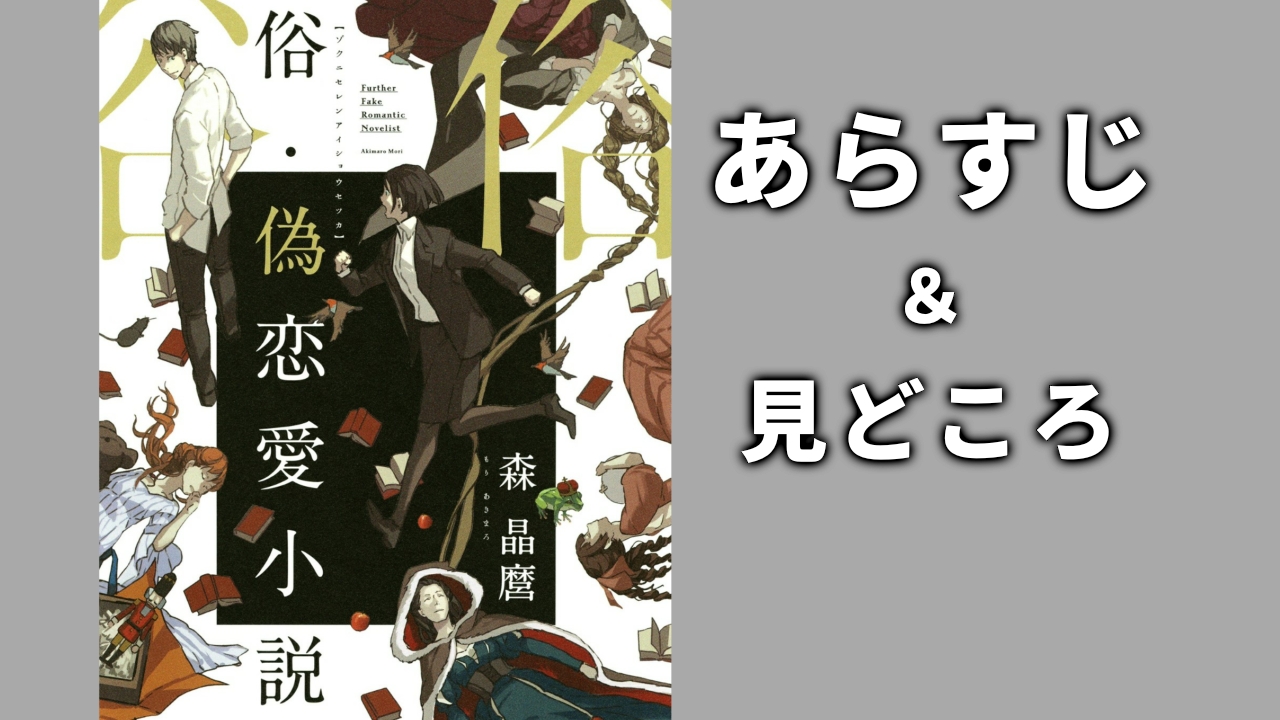ミステリーは好きだけど、人の死なない作品が読みたい。
そんな、名探偵コナンを毎週かかさず観ていたら、だんだん気持ちが鬱ぎみになってきて(毎週のように人がタヒぬので…)観るのをやめた筆者のような人におすすめなのが、
本作『田舎の刑事の趣味とお仕事』である。
本作には漫画『GANTZ』に登場するような首がふき飛ぶ場面や、はたまた横溝正史の金田一シリーズに出てくるような凄惨な、ともすればホラー要素の強めな殺害現場が出てこないことは保証する。
なにしろ、本作の第1話で登場する事件は、「ワサビの盗難」である。ワサビといえば蕎麦の汁に入れたりする、あのワサビである。
あんまり前置きが長くなってもあれなので、ここからはそんな本作の魅力を感想を交えつつ紹介していきたい。(もちろんネタバレには配慮して)
目次
シリーズの読む順番
紹介に入る前にいったん、本作も含めた田舎の刑事シリーズの読む順番をメモがてら書いておく。タイトルだけでは判別しにくいので。
以下の順番で読めばOK。
①『田舎の刑事の趣味とお仕事』
②『田舎の刑事の動物記』(旧版だと『田舎の刑事の闘病記』。文庫化に際してタイトルが改題されている。)
③『田舎の刑事の好敵手』
見どころ&感想
一見コミカルに見えるが、中身は本格派
1話目が先程も少し書いたように「ワサビ盗難事件」であったりと、一見コミカルに見えるが、
筆者がなんと言っても本作を気に入った一番の要因は、ひとつひとつの物語の謎解き部分の論理がよく練られていて、論理展開にずさんなところがないところである。
どういうことかというと、
ミステリーに分類される小説を読んでいると時々あるのが、ミステリー小説では当然主人公が謎を解くにあたって推理を展開するわけであるが、その時、この推理はちょっと強引すぎないか?とか、こじつけでは?とか、あるいは、論理の展開が一読では分かりづらく(これには筆者の脳みその問題もあるかもしれないが…それはともかく)、何回か同じ文章を読み直すことが時々ある。
本作には、そういった論理の杜撰((ずさん)さや、あるいは説明不足や省略がなく、非常に読みやすく、かつ、細かな論理展開が気になってしまう人でも満足できる内容になっていることが大変良いと思った。
つまり、まとめると、本作は、論理の本格さとエンターテイメントとしての読みやすさを両立させている点が大変良いと思った。
キャラクター同士のギャグテイストな掛け合いも楽しい
本作の作者はおそらく漫才やコントなどのお笑いが好きなんじゃないかというくらい、読んでいていてキャラクター同士の掛け合いにクスッとさせられることが多々あった。
例えば1つ紹介しておこう。
背景を簡単に説明しておくと、立てこもり事件が起き、なんと本作の主人公である黒川警部が人質としてとらわれてしまった時の話である。
課長やその部下達が立てこもっている犯人に対して、拡声器を使って呼びかけるのだが、そのあまりにも漫才じみたやり取りに(本人たちは大真面目なのである…)しびれをきらした犯人が思わず、
「真面目にやれ。どういう警察だ、お前ら」
引用:滝田務雄『田舎の刑事の趣味とお仕事』(創元推理文庫) p131
という切れの良いツッコミを入れているところなど筆者はツボだった。
回が進むごとにスルメのように味がでてくるキャラ同士の関係性
本作の主人公は黒川警部といって、頭のきれる優秀な男で、有事の際にはいつも頼りにされている人物なのだが、その部下に白石という男がいて、黒川警部いわく「バカ白石」と呼ばれており、いつも何かバカをやらかして上司である黒川警部に怒られているといったキャラクターなのである。
このおバカな白石がいつも頓珍漢な発言をしたり、何かやらかして、黒川警部から憤怒のような形相で怒られるというお決まりの流れが毎話ごとに繰り返されるのだが、読むうちに、読者として心地よさを感じてきて、まさに噛めば噛むほど味が出るスルメのような感覚があった。
ここからは完全に余談なのだが、リアルの世界でも、こういうことはあるよなと、ふと思った。いうなれば「いつも〇〇な人」みたいなやつで、例えば「いつも屁理屈を言う人」とか「いつも飲み会には来ない人」とかで、「そういうけど、お前いつも飲み会来ないじゃん、ハハハ」とか、「出た、〇〇の屁理屈」みたいな、
一見するとちょっとネガティブに捉えられがちなその人の特徴が、いい感じで「そういうキャラ」として周りから受け入れられているということがある。
そのキャラを貫いて、「この人はいつも〇〇だ」と周りから認識されることで、それが翻ってプラスに転じるというのだろうか。
上手くは言えないが、そうやって、キャラが立ってくると、いつもその人は「キャラに合致した一貫性のある振る舞い」をするため、周りからも行動に予想がつきやすく、安心感を与えることにつながってくるみたいな話を心理学の話題でみたことがあって、
誰しも集団内の人間関係で悩むことはあると思うが、こういう「〇〇キャラ」の話はそういった集団内での自分のポジションを確保するうえでヒントになるのではないかと思った。
実際に落とし込むとするなら、「いつも〇〇をするようにする」(○○に何を入れるかは自由)とかだろうか。
筆者だったら、いつも屁理屈を言うようにでもするかな。と、まあ、本の紹介から、かなり横道にそれたが、思い浮かんだのでついでに書いておこうと思って。弱小個人ブログだし、まぁ良いじゃろう。
っていうか、こんなことを考える自分って、よっぽど人間関係に悩んでるか、上手く行ってない(オット
おわりに
とても面白くて久々にハマって読んだ作品だった。本作はなんと嬉しいことにシリーズ化もされていて、まさに人生の楽しみが増えたという感じで嬉しい。
ここから少し話は変わるが、本作は、基本的に人の死なない日常系ミステリに分類されるはずで、筆者はこういう日常系のミステリ作品は好きなので、以前、「日常系ミステリ おすすめ」とかでググったことがあったのだけど、たしかその時見た紹介記事では本作は見かけなかった記憶があるのだが…。
そういったおすすめ記事を見て、
坂木司の引きこもり探偵シリーズとか、『氷菓』で有名な米澤穂信の古典部シリーズとか、あるいは北村薫の円紫さんシリーズとか、ひととおり有名どころは網羅したはずだったのだが、本作は見落としていたのか、それとも紹介されておらずマイナーなのか?いや、本作は2012年にドラマ化もされているし、そんなはずはないと思うのだが。