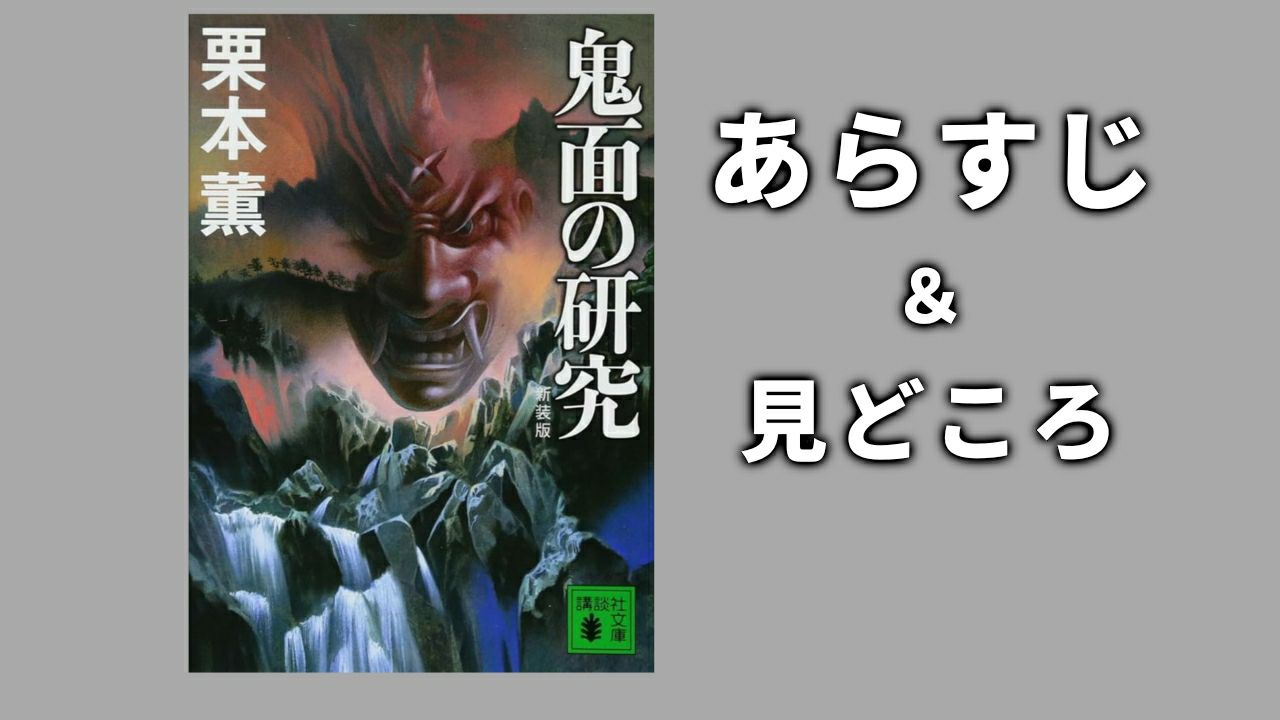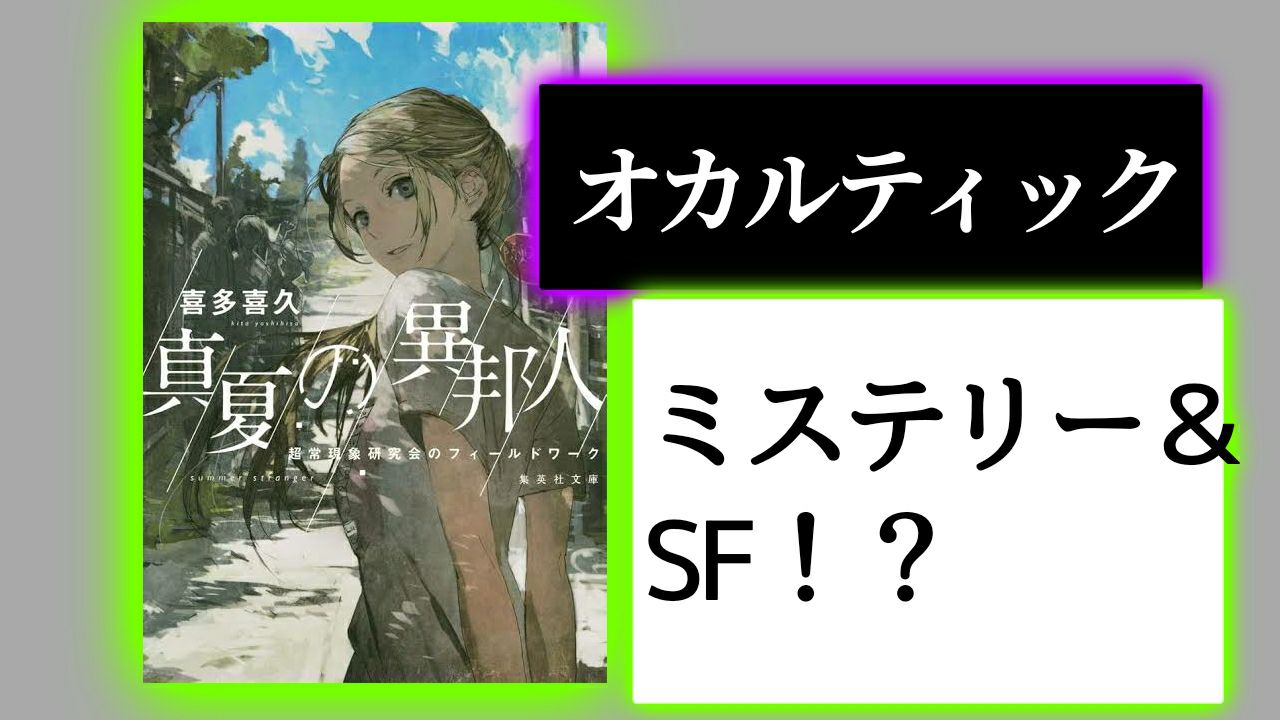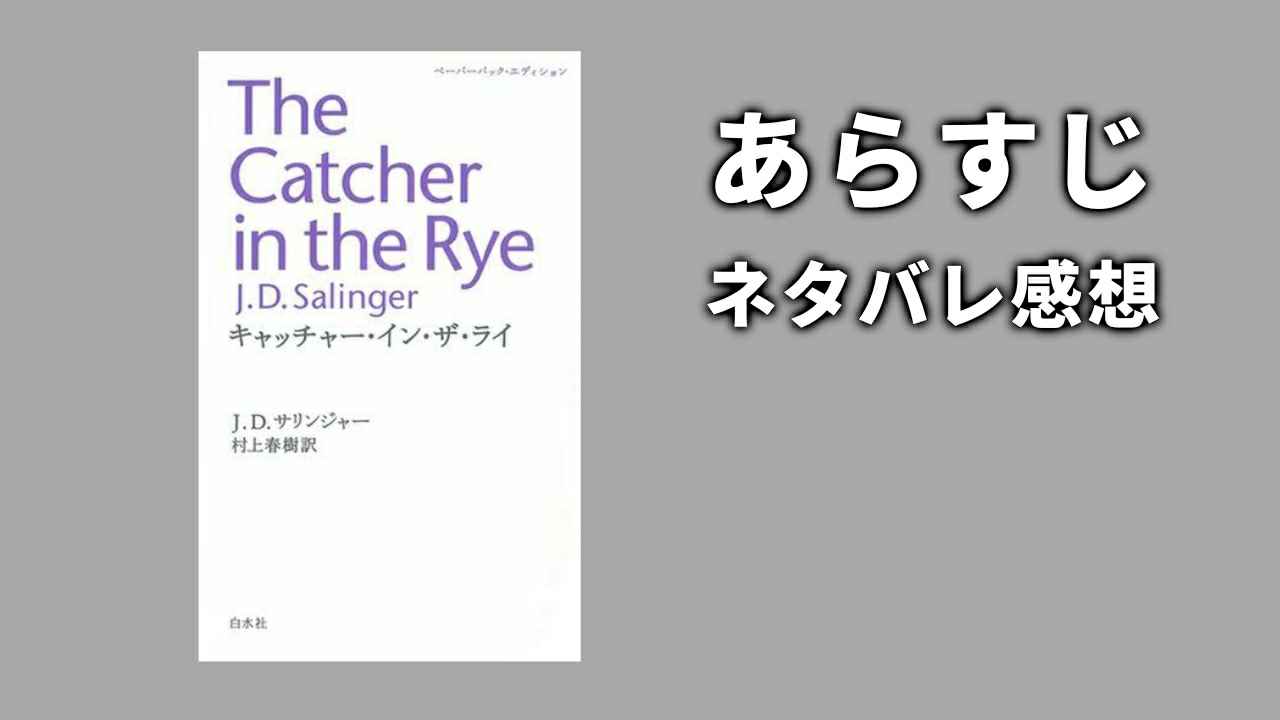前々から気になっていた作品。BOOKOFFにて入手できたので読んでみた。
本作『絃(いと)の聖域』は、探偵・伊集院大介が登場するシリーズの第1弾目にあたる。
以下、ネタバレは避けつつ、本作の紹介をしてみる。
目次
伊集院大介は「呪い」を解く探偵
「明智小五郎は謎を解く探偵で、金田一耕助は呪いを解く探偵だ」と誰かが言っていた。
本作に登場する伊集院大介は、後者で、まさに「呪い」を解く探偵だなと思った。
おそらく横溝正史の金田一耕助シリーズに少しでも触れたことのある人なら、本作を読んで、あの探偵、金田一耕助を思い浮かべると思う。
ただ、違うのは、本作の探偵である伊集院大介の場合、例えて言うなら、いくぶん現代ナイズされた金田一耕助であるということだ。
横溝正史の金田一耕助は、時代背景的に、終戦直後がその作品の舞台であるのに対し、
本作の伊集院大介は、現代がその作品の舞台なので、個人的に読みやすく、すんなりと物語の世界に入っていきやすいと思った。
(とはいっても、本作『絃(いと)の聖域』が書かれたのは昭和55年(1980年)なので、この記事を書いている2025年からすると、だいぶ昔に感じてしまうけれど)
とある一族にふりかかる呪い
さて、そろそろ本作の具体的な内容についても見ていきたい。
本作は、由緒ある三味線の名門の家で起こる事件を扱っている。
本作の準主人公的ポジションである山科(やましな)警部は、作品の舞台となる、その屋敷を指してこう言っている。
その古い家を出て、見慣れた机と、ふちのかけた湯呑みと、大迫警部のニヤニヤした顔にかこまれていると、奇妙な悪い夢をみていたものだ、という気になってくる。
(ここが、おれのいるところだ)
引用:栗本薫『絃の聖域』上 (講談社文庫)p55
事件の舞台となる、その屋敷に一歩足を踏み入れると、まるでそこは江戸の時代からそっくりぬけだしてきたかのような、現代からはまるで隔絶された空間が広がっているのであった。
そのまるで現代からは隔絶されたような、古めかしい屋敷で起こる、呪いめいた殺人事件と、複雑に入り乱れた人間模様・愛憎劇などなど。誠にじめじめとした、好きな人はどハマリすること間違いなしの要素がてんこ盛りである。
そして、その「呪い」を解き明かすのが、本作の探偵・伊集院大介となる。
愛嬌のある探偵
本作に登場する探偵、伊集院大介は、なんというかとても初々しい、愛嬌のある探偵として描かれている。こんな探偵はなかなかいないんじゃなかろうか。
以下、彼の初登場のシーンの描写を一部引用してみよう。
にこにこした、ちょっととぼけた笑顔、が、なんとなく、もうずっと前からかれを知っていたような─ひさしぶりで懐かしい友達に出会ったような、そんな気持ちをひきおこさせるのだ。
「いや、つまり── 何のご用でしたっけ」
山科は首をふって、わけもない微笑がこみあげてくるのを呑み下した。
引用:栗本薫『絃の聖域』上 (講談社文庫) p137
それからもうひとつ、初登場時の大介を印象づけるものとして、持ち前の口ぐせ「そんな気がした」がある。
山科の眉がけわしくなった。
「誰にききました。それを─まだ、今朝の新聞じゃそこまでは書いてない筈なんですがねえ」
「誰も、云わないです。ただぼく一寸、そんな気がしたもんで」
引用:栗本薫『絃の聖域』上 (講談社文庫) p138
「そんな気がした」。つい口ずさんでしまいたくなる言葉である。
しぶいおじさん警部補
あと、ほんとに個人的になのだけど、本作で語りを担当し、読者と一緒に事件を追っていく山科警部が、良い味を出していると思った。山科警部は、これまで幾度となく事件に立ち会ってきた年季の入ったベテラン警部なのである。かといって、変にでしゃばることもない。
どこにでもいそうな、読者と同じ目線を持った、だけど、少しだけ他の警部と変わっているといった感じの人物だ。
そして、山科警部補の方は、何百回となくやってきた、手慣れた順序の繰り返しだった。本庁を呼び、事情を説明し、何千人という客たちの扱いを苦慮し、楽屋口に警官を立たせてオフ・リミットにし、前後の事情を関係者にきく。
引用:栗本薫『絃の聖域』下 (講談社文庫) p225
おわりに
このたび何冊かの抜けはあるものの、BOOKOFFにて10数冊ほど、伊集院大介が登場するシリーズを入手できたので、他の作品も読み終わり次第、ぼちぼちと感想を書いていきたい。
ちなみにこの伊集院大介シリーズの読む順番が知りたいという人は、栗本薫『鬼面の研究 新装版』(講談社文庫)の巻末にある「伊集院大介シリーズ 著作リスト」が分かりやすくまとまっていて良い。